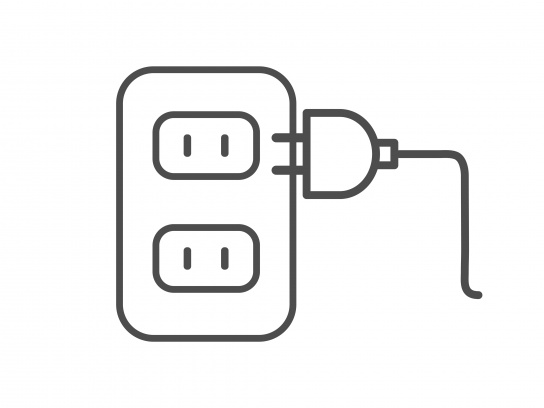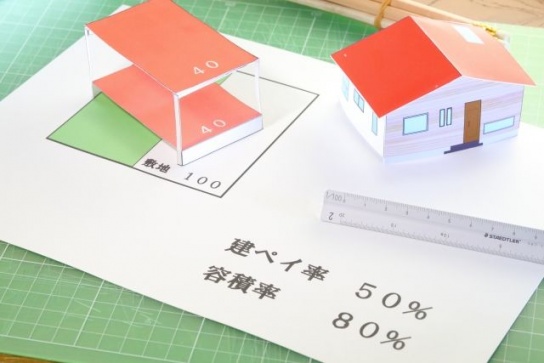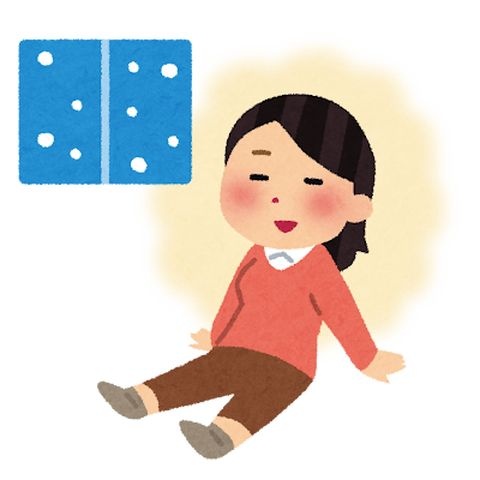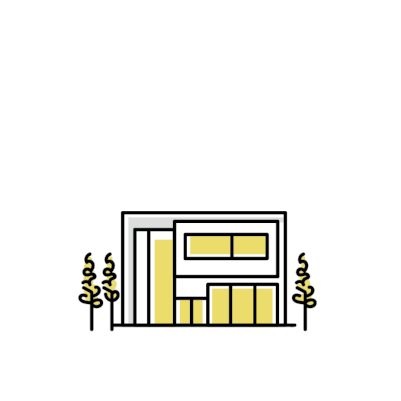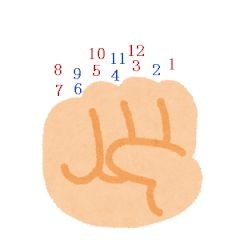2025/08/08
三和建設三和建設 静岡上棟住宅建築新築工事

先日の大安吉日にお客様のお家が上棟しました!
「上棟(じょうとう)」とは、主に木造住宅の建築において
柱や梁などの基本構造が完成し、屋根の最上部にある
「棟木(むなぎ)」を取り付ける工程を指します。
この作業は「棟上げ」や「建前(たてまえ)」とも呼ばれ、
地域や業界によって呼称が異なる場合があります 。
上棟は、建物の骨組みが完成し、棟木を取り付けることで、
建物の形がほぼ出来上がる重要な節目です。
この工程は、建築工事の中でも特に重要とされ、工事の安全
や職人への感謝を込めて「上棟式」が行われることが
あります 。
工事中、作業にあたる大工さんたちは図面を見ることなく
作業を進めていますが柱の位置はどうしてわかるん
でしょうか?
それは・・・
「番付」という柱や梁に記された位置目印があるからです!
建築現場で部材の組み合わせや配置を間違えずに行うための
大工さんの作業上の指標として使われます

横軸には「い・ろ・は…」(いろは歌の順)、縦軸には
「1・2・3…」
と付けられるのが一般的です。
たとえば、「い1」は横が「い」通り、縦が「1」通り
の交点にある部材、という意味です。
ちなみに慣用句で使われる「いの一番」という言葉は、
建築で最初に建てる柱である「い・1」に由来し、
「まっさき」「最初」という意味で使われるように
なったとされています

先日の上棟当日は40℃を超える猛暑でしたが無事に工程通り
作業が進みました!
大工の皆さん、ありがとうございました!
- YouTubeチャンネル更新中!こちらからチャンネル登録のほど、よろしくお願い致します。
https://www.youtube.com/channel/UCsbA8uOKp6SNUeOnrBZpdYA
- 三和建設静岡は、地域密着の不動産に強い土地からの注文住宅が得意です!快乾空間®発売中!
新着記事
タグ一覧
- すべて表示
- 完成見学会
- 静岡市
- ジェラート専門屋
- LA PALETTE(ラ パレット)
- フレンチカントリーテイスト
- 多層空間
- ワークスペース
- リフォーム
- プロムナード
- ドコリフォ
- 住宅施工事例
- 二世帯住宅
- 三和建設静
- イエタテ
- 公示価格
- 静岡県
- ランキング
- 東京都
- 1位
- 清水区馬走
- 料理
- リノベーション
- 静岡市スイーツ
- カレンダー
- 暦
- 修理
- お問合せ
- 三和建設静岡市
- 株式会社大仙
- 静岡市グルメ
- 蕎麦屋
- グルテンフリー
- 鴨料理
- 住宅テイスト
- 説明会
- オンライン
- 対面
- 清水
- 水回りリフォーム
- 静岡住宅会社
- 用宗オススメスポット
- 菜の花
- 春
- メンテナンス
- 住宅
- プレゼンハウス
- 見学会情報
- リビング
- 吹抜けリビング
- アンダーリビング
- タイピング
- 単語登録
- 新築
- 水回り
- 給湯機
- ルピシア
- お茶
- 建設
- 桜
- 円安
- ドル高
- 為替
- 投資家
- 建築材料
- 日本経済
- 設備器具の納期
- ガスコンロ
- 照明器具
- 4月
- 新しい
- オープン
- 健康
- 温環境
- 春野菜
- 春大根
- 子育て応援住宅
- S-BOX
- 無垢材
- 不動産
- 土地
- 注文住宅
- 低体温
- 血流
- 子供部屋
- 筍
- マイホーム
- 賃貸
- 比較
- メリットベメリット
- 静岡市ラーメン
- なすソバ
- 中華料理屋
- 地元グルメ
- AKEBONO La Table
- S-BOX
- 洗濯
- ハンガー
- ストッパー
- 自由設計
- 工務店のメリット
- 住宅会社の選び方
- ウッドショック
- 価格高騰
- 値上げ
- ネモフィラ
- カウネット
- カウコレプレミアム
- 便利グッズ
- 花畑
- SDGs
- 長寿命住宅
- CO2削減
- 環境汚染抑制
- 街づくり
- 建てる
- 若い時
- 理由
- ランドリールーム
- 共働き
- 家事
- 建築
- 和風
- 快適な住宅
- 平屋
- 清水第二中
- インスタグラム
- 工務店の日報
- Youtube
- ウッドデッキ
- おうちキャンプ
- アウトドア
- 住宅ローン
- こどもの日
- 鯉のぼり
- 鎧兜
- クールビズ
- 夏
- 期間
- 服装
- 観光スポット
- 古民家カフェ
- 焼津市
- トイレ
- 窓の設置
- メリット・デメリット
- デメリット
- ハンディチョッパー
- 回遊動線
- 内装
- 外装
- ポイント
- カフェ風キッチン
- 昼食
- お好み焼き
- オタフク
- 地域密着
- 静岡不動産
- ワンフロア
- 保証
- 注意点
- 造作キッチンカウンター
- コストダウン
- 求人
- 総務職
- 募集
- 新卒
- 中途
- 収納
- インテリア
- 調理家電
- 窓
- サッシ
- サーモスⅡ-H
- LIXIL
- 静岡中部家づくり
- 先輩お施主様の声
- 5月
- GW
- 潮干狩り
- 五月病
- 梅雨
- 傘
- 雨
- カビ対策
- 梅雨入り前
- 観葉植物
- 電子帳簿保存法
- 請求書
- 電子化
- 緑のある暮らし
- ペンダントライト
- スタンドライト
- 雰囲気を変える
- 静岡三和建設
- フェンス工事
- 境界線
- 駿河区敷地
- 家の外観
- ビール
- 10月
- バーカウンター
- ホームバー
- おうち時間
- 紫陽花
- 花言葉
- お施主様の声
- 人気
- 設備
- 三和建設㈱
- 造作洗面台
- 玄関ポーチ
- ぴよりん
- うちっちぴよりん
- 清水区食べ物屋
- まるさ商店
- 魚介豚骨ラーメン
- 北欧
- デザイナー
- 椅子
- いつから
- 過ごし方
- コクヨ
- GLOO
- 夏越の大祓
- 茅の輪
- 人形
- 無病息災
- 父の日
- プレゼント
- 19日
- 用宗
- おでかけスポット
- 東海大海洋学部博物館
- 静岡市観光
- 清水の水族館
- 清水区おでかけ
- こどみらい住宅支援
- 契約
- 建物
- 家電
- 登記
- 建売住宅
- 埼玉
- メッツァ・ビレッジ
- トーベ・ヤンソン
- 快乾空間
- 梅雨の洗濯
- 室内干し
- 熱中症
- 対策
- 6月
- 電話番号
- ルームツアー
- 畳
- 調湿効果
- 7月25日
- グランシップ
- 就職フェア
- 外壁
- 色分け
- サイディング
- ツートン
- 清水マリナート
- 田中達也
- ミニチュアライフ展
- 七夕
- 7月7日
- 由来
- ZEH
- 住宅ローン控除
- 太陽光発電
- 2024年
- 確認申請
- 子育て世代
- ママ
- 動線
- おすすめ映画
- コメディ映画
- 静岡第一テレビ
- TV出演
- ピン★スポ
- 総務
- 間取り
- イベント
- 安倍川花火大会
- 2022
- 移住
- 就職支援金
- しずおか就職net
- 置き配
- 荷物
- 換気システム
- せせらぎ®
- 熱交換
- パッシブデザイン
- アクティブデザイン
- 自然
- 自動販売機
- 子ども食堂
- 共食
- 職業人インタビュー
- 静岡商工会議所
- 高校生
- 不動産投資
- 投資
- カーペット
- ゴム跡
- フローリング
- 掃除
- アラジン
- トースタ―
- 秋
- 吹き抜け
- スケルトン階段
- チラシ配り
- 模様替え
- 空き家
- 問題
- スリットシャッター
- 防災の日
- 防災グッズ
- キャンプ用品
- 代用
- PayPay
- キャンペーン
- 2023卒
- 会社説明会
- 9月病
- 季節変わり目
- 最低賃金
- 中秋の名月
- 9月10日
- 入江南町
- コスモス
- 秋桜
- おでかけ
- 現地説明会
- 分譲地
- 台風
- リスク
- フリーマガジン
- 台風15号
- 10月3日
- 中古住宅
- インスペクション
- 瑕疵
- 住宅の構造
- 台風被害
- 精油
- アロマセラピー
- ラベンダー
- 睡眠
- 不眠
- IFPAアロマセラピスト
- ヘルニア
- ブロック注射
- トリガー注射
- 防災
- 非常食
- マッシュポテト
- じゃがマッシュ
- 駿河区高松
- うどん屋
- こころ彩
- 旅行
- 支援
- 全国旅行支援
- 冬支度
- エアコン掃除
- 北朝鮮
- ミサイル
- Jアラート
- パトリオットミサイル
- PAC-3
- ショート動画
- 瀬名Cプレゼンハウス
- 新卒採用終了
- 中途採用継続
- 物件購入
- 匠宿
- 陶芸
- 竹細工
- さつまいも
- 収穫
- 食べごろ
- 清水区建設会社
- 調湿作用
- シャープ
- 蓄電池
- 被災者支援
- 被災者生活再建支援制度
- 自然災害
- 改正省エネ基準
- 長期優良住宅
- UA値
- シロアリ駆除
- 消毒
- 臭い
- 転職
- 転職情報サイト
- デューダ
- ベビーゲート
- 転落防止
- 住宅設備
- 水災
- 静岡市建設会社
- 日本平ホテル
- 富士山
- 水害
- 保険
- 部屋作り
- お家づくり
- ダウンライト
- シェルターハウス
- 戦争
- 日本
- コンセント
- 下水
- 解決
- サッカー
- ワールドカップ
- スペイン戦
- 地盤調査
- 地盤改良
- ANDPAD
- 施工管理アプリ
- 業務改善
- クリスマス
- 室内
- 不動産購入
- 融資
- 金融機関
- 復旧工事
- 補助申請
- 建築指導課
- 家
- シンボルツリー
- 庭
- シマトネリコ
- オリーブ
- ボーリング調査
- スウェーデン式サウンディング調査
- 秋葉山祭り
- お祭り
- 年末
- 大掃除
- 効率的
- 台風15号
- 支援金
- 経費削減
- 増えてきた
- 年賀状
- どんど焼き
- 正月飾り
- 新紙幣
- タンス預金
- 課税
- 2024
- お正月
- 鏡餅
- 鏡開き
- 二十四節気
- 大寒
- 乾燥
- 火事
- 金額
- LDK
- 静岡三和
- 電気料金
- 高い
- いつまで
- 湿度
- 勾配天井
- 結露
- 対策方法
- 建売
- 静岡
- 最高気温
- 断熱
- 吹抜け
- 地震
- 耐震等級
- 阪神淡路大震災
- 東日本大震災
- 花粉症
- 症状
- 階段
- 種類
- 吉田町
- 小山城
- どうする家康
- 愛犬と暮らす
- ペット
- トイプードル
- 犬の怪我
- 先進的窓リノベ
- 補助金
- インプラス
- 電気代高騰
- ヒートショック
- 借景
- 景色
- ハイドア
- ドア
- 木造住宅は弱い
- 木造住宅は強い
- 祭り
- 東海道
- 丸子宿
- エアコン
- 室外機
- トラベル
- 電気代
- 節約
- 掲載
- 三和建設(株)
- イエタテ静岡
- 住宅紹介
- お酒
- 肝臓
- 飲み会
- 特定空き家
- 固定資産税
- リノベ住宅
- 浄化槽
- 新入社員
- 自動車
- タイヤ
- 交換時期
- ローン金利
- 黄砂
- PM2.5
- 三
- 人体被害
- エスパルスドリームプラザ
- エスパルス
- 船とハナウタ
- 基礎
- 鉄筋
- サビ
- 不良品
- 防水
- FRP防水
- ベランダ
- ストレス
- ツボ押し
- マスク着用
- コロナ
- 誕生花
- 馬走
- LEDライト
- パソコン
- 時短
- 下地
- DIY
- 柱
- TOTO
- きれい除菌水
- 次亜塩素酸
- イエタテ2023夏号
- ショートカット
- 清水みなと祭り
- 花火
- 火災
- 木造と鉄骨造
- 特別企画
- 社長の年齢分析
- 後継者不足
- 後継者倒産
- 社長引退
- 生シラス
- 建築基準法改正
- 2025年
- 脱炭素社会
- 4号特例の廃止
- 被災者生活再建支援金
- 自転車
- ヘルメット
- 盗難
- 防犯対策
- ウイリアム・モリス
- 壁紙
- カーテン
- 避難場所
- 震度
- キッチン
- ワークトップ
- ショウルーム
- 青春18きっぷ
- JR
- 電車
- 失敗
- 感謝
- 成功
- 三和健設
- 改正空き家対策
- 空き家管理
- 活用
- インボイス
- 消費税
- ガソリン車
- 電気自動車
- 販売停止
- ハイブリット車
- 営業
- 設計
- ラーケーション
- 愛知県
- 保護者
- 家族サービス
- 疲労回復
- 運動
- アクティブレスト
- がん
- 生存率を高める
- 病院
- 癌
- 10月5日
- 大阪万博
- 予算
- 人件費
- チョコザップ
- ジム
- ダイエット
- 税金
- 減税
- 印紙税
- 不動産取得税
- 空間シリーズ
- 美誂空間
- お刺身
- 一期
- お魚
- HP
- リニューアル
- 写真撮影
- ベランピング
- 花粉
- アレルギー
- 結膜炎
- 扉
- 丁番
- 調整
- ガブリチキン
- 唐揚げ
- ハイボール
- ナチュラル
- モダン
- リンサークリーナー
- アイリスオーヤマ
- 天井
- ビルトイン食洗機
- ワイドタイプ
- 新発売
- パナソニック
- セミナー
- お風呂
- TOTO YKK AP
- DUSKIN
- ダスキン
- 解熱材
- 鎮痛剤
- 熱冷まし
- ロキソニン
- アセトアミノフェン
- 資金計画
- 住宅ローンアドバイザー
- 大蔵持
- 効率化
- 相談会
- 夜
- お菓子詰め放題
- TikTok
- 動画
- ダニ
- トコジラミダニ
- おかし詰め放題
- パーツギャラリー
- ホームページ
- 喪中
- 神棚
- 神棚封じ
- 木造住宅
- 倒壊
- 新耐震基準
- キャッシュレス
- 水素水
- アンチエイジング
- 抗酸化作用
- 構造計算
- 皮膚の乾燥
- 健康問題
- 塗料
- 光触媒
- 親水性塗料
- キッチンカー
- 抽選会
- お菓子プレゼント
- 造作額
- 清水区
- にゃんこ
- ネコ
- アイディア
- 宅配ボックス
- こどもエコ住まい支援事業
- 雨水タンク
- 断水
- 構造
- コーヒーの種類
- ブラジル
- キリマンジャロ
- コロンビア
- ひな祭り
- お雛様
- 片付け
- 吊るし雛
- 整理収納
- 設計相談会
- 13年
- 安井金比羅堂
- 京都
- 悪縁を絶つ
- お参り
- 三和建設静岡
- 現場シート
- 足場幕
- マイナス金利
- 景気
- 25卒
- 静岡耐震助成金
- TOUKAI-ゼロ
- 地震対策
- 住宅購入
- 規格住宅
- 入学式
- 玄関
- 鏡
- 新卒採用
- ニュータウン
- 高齢化
- 問題点
- マイナンバーカード
- 健康保険証
- マイナ保険証
- クリーンシェルター
- 熱中症アラート
- HEAT20
- 断熱省エネ基準
- 虫対策
- 室内外
- 七ツ新屋
- 幸せホルモン
- ジャルディーノ
- オムライス
- 敷地
- 愛犬
- ドッグラン
- ボーナス
- 経済
- 財務管理
- モチベーション
- 静岡三和建設株
- 建物見学
- 予約受付中
- 窓のメリット
- 静岡市三和建設株式会社
- 雰囲気
- 湿気
- 管理
- 家を傷めない工夫
- フェイクグリーン
- 選び方
- エレキギター
- アコースティックギター
- 原宿
- 暑さ対策
- シート
- シェード
- 冷房費削減
- リクシル
- 窓ガラス
- 目隠し
- 基礎工事
- コンクリート
- コンクリートの割れ
- 静岡三和建設株式会社
- 災害地域
- 洪水地域
- 土砂災害警戒区域
- 津波災害地域
- 浸水地域
- 採用
- 還元イオン整水器
- 酸性水
- 手足口病
- 警戒レベル
- くふうイエタテ
- 中部地区
- 人気ランキング
- 住宅情報
- オリンピック
- セーヌ川
- パリ
- 富士通ゼネラル
- 清掃
- カビ
- 散歩時間
- ワンちゃん
- 犬
- 営業職
- 南海トラフ地震
- 地震準備
- 避難
- 心理バイアス
- 正常バイアス
- 火災報知器
- 義務
- 中途採用
- 住宅営業
- インテリアコーディネーター
- 転勤なし
- 台風10号
- 秋雨前線
- 避難勧告
- コメ金額
- 消費者物価指数
- 縁日
- 十五夜
- お月見
- お供え
- へそもち
- 耐震補強
- 学内企業説明会
- 英和学院大学
- 常葉大学
- 熊
- クマ
- 温暖化
- 郵便料金
- 10月1日
- 自民党総裁
- 石破総裁
- 金利
- ガクチカ
- 学生時代
- 面接
- 用語
- グミッツエル
- カンロ
- 床暖房
- ヒートポンプ式床暖房
- ガス温水式床暖房
- 静岡市三和建設
- webご祝儀
- 結婚式
- ドライクリーニング
- 衣替え
- 文化の日
- 地震の死因
- 地震保険
- 保険の支払い
- 魅力
- 冬
- 清水エスパルス
- 応援グッズ
- プレゼンハウス見学
- 勤労感謝の日
- 11月23日
- エアコンの寿命
- エアコン清掃
- 寒さ対策
- 床
- 部屋
- 強盗
- 防犯
- 護身
- 三和建設(株)
- いい夫婦の日
- 夫婦岩
- 天照大神
- 高校
- 見学
- 思い出
- 夜の見学会
- 1人の時間
- 心のリセット
- エネルギーの回復
- 晦日
- 大晦日
- 違い
- 1月
- 静岡市清水区
- 風呂場の事故
- 血圧
- 中山美穂
- 簡単
- 手作り
- エコカラット
- 湿気対策
- 調湿性能
- 正月飾りの時期
- 水道が出ない
- 給湯設備
- 住環境
- 生活動線
- 家相
- 2/9
- 地鎮祭
- 造作家具
- ポスト
- 便利
- 配置
- 書斎
- 三和建設株式会社
- 寝室
- 政策
- パントリー
- トイレの悩み
- 尿はね
- 悩み解消
- 内窓リフォーム工事
- 太陽光発電システム
- 三和建設
- 省エネ
- 再生エネルギー
- 外壁塗装
- 塗り替え
- タイミング
- 階段下
- カウンター
- 樹種
- 愛犬家
- 床材
- 水まわり
- ペットと暮らす
- シーリングファン
- 空気循環
- 床選び
- 足ざわり
- 家の中の乾燥
- ダウンリビング
- ピットリビング
- スロップシンク
- 雨の日
- 乾かない
- 愛猫と暮らす
- 興津
- バルコニー
- 和室
- 家具
- 静岡 三和建設
- パイン材
- ヒノキ材
- スギ材
- たこ足配線
- 発火防止
- 工務店選び
- ハウスメーカー選び
- やりたい箇所
- 天然芝
- 人工芝
- ガーデニング
- 塗り壁外壁
- 子供主体
- 成長
- アカシア
- 広葉樹
- 建築化照明
- 始め方
- いつ
- 北向き道路
- 陽当たり
- トップライト
- 津波
- 洗面
- おしゃれ
- こだわり
- 静岡銀行
- 資産運用
- 保険見直し
- 5/10・11限定
- 三和建設 静岡
- 窓の選び方
- 2025年
- 川原町
- 月見町公園
- 岡小
- 花みずき通り
- 構造見学会
- 葵区古庄
- モルック
- 梅雨の湿気対策
- 快適
- 空間
- 提案
- 境界
- 不動産売買
- 家を建てるとき
- 米不足
- 住宅造り
- 米不足対応
- 自治会
- 近年
- コスト
- 見学会
- 愛犬と住む家
- 愛犬の安全確保
- 洗面室
- 脱衣室
- 買取査定
- 土地情報
- プラン作成
- 過ごす
- 防虫
- 高断熱
- 第一種換気システム
- WITH CAT
- キャットウォーク
- くぐり戸
- 食欲
- 冷房
- 愛犬と住む家づくり
- 散歩ケア
- 外構工事
- 植栽計画
- 静岡で家を建てるときに読む本
- 小さな工事
- 水漏れ
- ロフト
- ガレージ
- 趣味
- ヌック
- 子供の転落事故
- 落下防止
- 間取り相談
- トイレ手洗い
- ミラタップ
- ショールーム
- 高齢者
- 暮らし
- 感震ブレーカー
- リフォーム工事
- 日射遮蔽
- トイプードルと暮らす
- インナーバルコニー
- 猛暑
- 特定小型原動機付自転車
- キックボード
- 三和建設清水区
- 西小川
- 家具選び
- 三話建設静岡
- 給湯機入替
- 26卒
- 27卒
- 仕事体験
- 新築工事
- 上棟
- 8月30日
- 耐震性
- 生乾き臭
- With Cats
- 高性能住宅
- 健康住宅
- 住宅に求めるもの
- 家づくりの最初
- 神事
- 残暑
- ルームエアコン
- 家を持つ
- 資産
- 安心
- 建ぺい率
- 容積率
- 土地探し
- 建築基準法
- 敷地面積
- 耐火建築物
- 延べ床面積
- 事前準備
- ケイミュー
- システムバス
- 癒しの空間
- 9/20・9/21イベント
- 無垢床材
- 基準地価
- 土地価格
- 清水区船越
- 営業のお仕事
- い草
- 部屋干し
- 人気エリア
- 子ども
- 家族
- 集う
- 無垢の床材
- 自然素材
- 亜熱帯化
- 収納スペース
- 新築住宅
- 造作洗面
- 静岡市 分譲地
- 新規分譲
- 猫と暮らす
- キャットタワー
- 狭小住宅
- 狭土地
- 住宅省エネ2025キャンペーン
- 高層ビル
- はしご車
- 下がり天井
- ルーバー天井
- 空間づくり
- ホテルライク
- いえづくり
- アイデア
- ドラマ
- 北側斜線
- 改修
- 軒天
- シーリングライト
- ブラケットライト
- 建築用語
- こけら
- 几帳面
- 2階LDK
- アウトドアリビング
- ユニットバス
- 三和建設 静岡、無垢床材、ドックラン、古庄、敷地
- 三和建設 見学会
- クロス
- アクセントカラー
- アースカラー
- AI
- 家づくり
- 家事動線
- クマの目撃
- みらいエコ住宅
- 2026
- 耐震
- 軽量化
- 住宅ローン減税
- フロアタイル
- 壁仕上げ
- テレビ背面
- 三和建設 静岡市
- オープンハウス
- 造作空間
- 住宅の歴史
- 年末年始
- センサーライト
- 暖房機器
- 災害
- 有効スペース
- 2026年
- 干支
- 洗面化粧台
- 造作洗面化粧台
- 正月
- お飾り
- 駿河区谷田
- 5区画分譲
- 県立美術館前駅
- 風向
- コーチパネル
- 棟上げ
- 感動
- 実感
- 上棟式
- 壁掛けテレビ
- 静岡市 三和建設
- 清水区 不動産
- 袖師小学区 土地
- 六曜
- 節分
- 雪
- 住宅関連
- 外観
- 販売地
- 建築条件付き
- 駿河区
- 光陽町
- 用途地域
- 都市計画法
- 建替え
- 不動産売却
- 居住用財産の売却特例
- 電気設備
- 三話建設 静岡
- 2階リビング